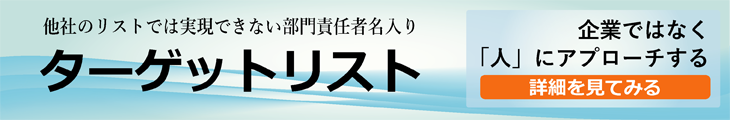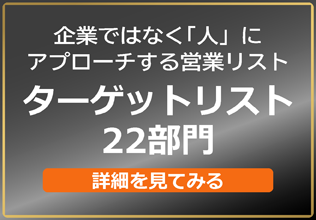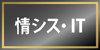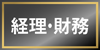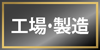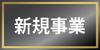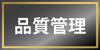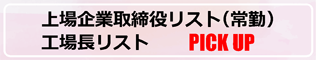2025-04-24
検索はもう「探す行為」ではなくなる? AI Overviews が変える情報との向き合い方
BtoB 営業・マーケティング コラム
私たちは日々、無数の「検索」を通じて情報と接しています。製品やサービスについて調べたり、専門的な知見を求めたり、仕事の合間にちょっとした疑問を解消したりと、検索行動は日常の中にすっかり溶け込んでいます。その検索体験が、今まさに大きな転換期を迎えようとしています。
Googleが提供を開始した「AI Overview(旧:SGE=Search Generative Experience)」は、生成AIを活用した新しい検索体験の仕組みです。従来のように検索結果の一覧から必要な情報を探しに行くのではなく、検索した瞬間にAIが要約や解釈を提示するというアプローチが特徴です。この変化により、検索が果たす役割やユーザーの行動フローそのものが再定義されつつあります。
こうした変化は、単なる検索技術の進化ではなく、企業や組織がどのように情報を発信し、どのように信頼を築いていくかという視点にも深く関わってきます。検索体験の変化は、情報が流通する構造に影響を与え、ひいてはビジネスの在り方そのものを問い直すことにつながるかもしれません。
本記事では、検索体験の構造が変わることによって、どのような波が企業や社会にもたらされるのかに焦点を当てて考えていきます。検索の前提が変わったとき、私たちはどう変わるべきなのか。いま、その問いに向き合う必要があります。
目次
「検索」の再定義 ― アクションの前に答えがある世界
かつて「検索する」という行為は、情報にたどり着くための出発点でした。何を知りたいのかを自分の中で整理し、キーワードを入力し、表示された検索結果を一つずつ確認していく。それが、私たちにとって自然な情報探索の流れでした。
しかし、生成AIを活用した AI Overviews の登場により、この構図は大きく揺らぎ始めています。検索結果が表示される前に、AIが自動で関連情報を要約し、問いに対する一つの“回答”を提示する。つまり、ユーザーがリンクをクリックする前に、ある程度の結論や方向性を得てしまうという体験が、当たり前になりつつあります。
この変化は、検索を「出発点」から「目的地」に近づけてしまう可能性をはらんでいます。検索というアクションが、もはや探すための行為ではなく、判断するための行為へと姿を変えつつあるのです。そしてそれは、ビジネスにおける情報発信やユーザーとの接点の意味合いにも影響を与えます。
従来の検索は、ユーザーの能動性に支えられていました。複数の情報源を比較し、自らの文脈に引き寄せながら解釈していくプロセスが存在していたからです。ところが AI Overviews のような仕組みが前提となると、情報の「探索」よりも「受容」に重きが置かれやすくなります。結果として、企業や組織が発信する情報は、「ユーザーに読まれるか」ではなく、「AIに引用されるか」「要約されやすいか」といった別の軸で評価される場面が増えていくでしょう。
つまり、検索という行為の再定義は、単に検索技術の進化を指すのではなく、情報と人との関係の変質を意味します。ユーザーが行動を起こす前に答えを得る ―― そんな世界では、情報をどのように提示するかが、従来とはまったく異なる影響力を持つようになるのです。
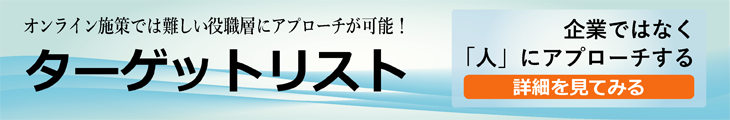
情報流通の重心が変わる ― 組織に問われる提供者としての構え
これまでのインターネット検索における情報流通は、検索エンジンが情報の入り口でありながらも、ユーザーが自ら複数のページを訪れ、必要に応じて深掘りしていくという「分散的」な構造を前提としてきました。情報発信者である企業やメディアは、検索結果に表示されること、あるいは自社サイトへの流入を獲得することに注力し、その後の閲覧や行動を促す仕組みを整えてきました。
しかし、 AI Overviews によってこの流れに変化が生まれています。AIが検索意図に応じた複数の情報を収集し、それをひとつの回答として再構成するため、ユーザーは個別の情報源をたどる前に「まとまった知見」に触れることになります。つまり、情報の「集積点」がユーザー側の行動によってではなく、AIによって前もって生成されるようになるのです。
この変化により、情報流通の重心は、ページ単位のアクセスから、文脈の中で「参照される」情報の価値へと移行していきます。誰が発信したか、どのページに掲載されているかという「場所」の重要性よりも、どのように言語化され、他の知見とどのように結びつくかという「内容と構造」の方が重みを持ち始めるのです。
その結果、企業や組織にとっては、情報提供のあり方そのものを見直すことが求められます。単に検索上位に表示されることや、一貫したブランディングに努めるだけではなく、「信頼に足る情報を誰にでも理解できる形で届けているか」という問いが、より本質的なテーマになっていくでしょう。
また、情報を発信することと、信頼されることは、これまで以上に切り離して考えられるようになります。AIが要約の中でどのように情報を取り扱うかは、検索順位のように数値で測ることが難しく、代わりに情報の整合性や表現の透明性が鍵になります。文章の曖昧さや論点の不在が、そのまま「引用されない」という形で跳ね返ってくる構造です。
情報の「発信元」ではなく「文脈における位置付け」こそが価値を生む。この構造の変化に対して、どれだけ早く気づき、どのように備えるかが、今後の情報提供者としての信頼と影響力を大きく左右することになります。
意思決定プロセスの影響 ― 検索が行動設計に先行する時代
情報収集から意思決定に至るまでのプロセスは、これまで一定のステップを踏むものでした。何かを検討しようとするとき、まずは自分の知識や前提をもとに検索し、複数の選択肢を比較・検討しながら、自分なりの納得感を積み上げていく。こうした段階的なプロセスは、特にビジネスシーンにおいては慎重さを担保する手段でもありました。
ところが、 AI Overviews のような生成AIによる要約提示が前提となると、意思決定の土台そのものが変質していきます。ユーザーが自ら情報を収集する前に、AIが“十分に納得できる答え”を用意してくれる世界では、比較や検討のプロセスが短縮・簡略化されることが多くなるからです。これは、行動の設計において「判断」が「探索」に先行する構図を生み出します。
たとえば、あるソリューションを導入するかどうかを検討する際、本来であれば複数のサービスを比較し、特徴や価格、サポート体制などを照らし合わせて判断するはずです。しかし、検索の時点でAIが「このような場合にはA社のソリューションが有効です」といった形で要約を提示すれば、それが判断の出発点になる可能性があります。ユーザーは比較を飛ばして、提示された答えを前提に次の行動を設計してしまうのです。
この構図の変化は、企業にとって大きな意味を持ちます。従来は「比較検討の場」に入り込むことを目指してきた企業が、今後は「最初に提示される情報群」の中にどう存在するか、という問いに向き合うことになります。そしてその問いは、単なる情報露出の問題ではなく、自社の提供価値をどれだけ言語化できているか、他と紛れないかたちで位置づけられているかという、本質的な取り組みを必要とします。
さらに言えば、こうした検索体験の変化は、社内の意思決定スタイルにも影響を及ぼします。部門間の合意形成や説明責任のプロセスにおいて、「検索して出てきた内容」による先入観が無意識に共有されることで、議論が一定の方向に誘導されるリスクも無視できません。判断の出発点がAIによって“整えられている”状態では、その判断の前提に自覚的であることが重要になります。
つまり、検索の役割が「行動のきっかけ」から「行動の設計図」へと変わるいま、企業には情報の受け手に対する新しい責任が生まれつつあるのです。
インターフェースが変える企業とユーザーの距離
これまでの検索は、テキストボックスにキーワードを入力し、並んだリンク群を選びながら情報へとたどり着く、非常に「操作的」な体験でした。ユーザーはある意味で検索エンジンのインターフェースを「使いこなす」ことで、必要な情報にアクセスしていたわけです。そこにはある種の距離感があり、企業や組織が提供する情報とユーザーの間には、検索というフィルターが明確に存在していました。
AI Overviews のような生成AIを基盤とした検索体験が広がることで、この距離感が根本から変わろうとしています。従来のリンク集に代わって、検索キーワードに応じた要約や提案がAIによって直接提示されます。ユーザーは「探す」ことなく、「聞く」ような感覚で情報を得るようになります。検索はもはや“機能”ではなく、“対話”に近づいてきているのです。
このインターフェースの変化は、企業とユーザーの関係にも新たな問いを投げかけます。従来はWebサイトやSNSといったチャネルを通じて「会いに来てもらう」構造だったのに対し、これからはユーザーがどこにいても「先回りして応える」ことが求められる構造に移り変わります。検索というチャネルにおける距離が縮まるというより、「仲介」が消える、そんな感覚に近いかもしれません。
その結果、情報が届くスピードだけでなく、情報を介して生まれる印象の即時性も増していきます。ユーザーが目にするのは、企業が用意したページではなく、AIが構成した説明文や要約であるため、企業がどのように見えるかは、自社が提供する情報の「素材としての質」に大きく依存することになります。つまり、コンテンツそのものの良し悪しよりも、それが「第三者の視点でどうまとめられるか」が、最初の印象を左右するようになるのです。
企業とユーザーの距離は、縮まっているようで、実際には「誰がその情報を組み立てているのか」がブラックボックス化していく時代でもあります。その中で、企業が果たすべきは、透明性と一貫性のある情報提供と、誤解されにくい言葉選びです。接触の形が変わるからこそ、情報そのものの伝達精度が、これまで以上に関係性に直結していくのです。
まとめ
Googleが提示した新しい検索のかたち、AI Overviews は、単なる検索技術の進化という枠にとどまらず、情報の扱われ方や、ユーザーの意思決定のプロセス、さらには企業と社会との接点の構造にまで影響を及ぼし始めています。
AI Overviews では、ユーザーが検索結果にアクセスする前に、AIが要約した回答に触れることになります。その結果、「検索して調べる」から「検索して答えを見る」へという転換が進行しており、検索は情報の入口というより、すでに選別された情報の提示点として機能する場面が増えています。
この変化は、企業にとっても見過ごせないものです。従来のように、自社サイトやコンテンツにユーザーを呼び込んでから関係を築くという流れが崩れ始めているからです。情報は、企業が発信したとおりに届くとは限らず、AIが再構成し、異なる文脈の中で引用されることが当たり前になってきています。
生成AIが介在する情報環境では、「発信した内容そのもの」よりも「どのように再構成されて伝わるか」が先に立つことがあります。そのため、情報の扱い方や整理のしかたを、従来の枠組みのままで維持していくことが、どこかの段階で足かせとなる可能性は否定できません。
また、検索体験の変化は、ユーザーの意思決定プロセスにも影を落とします。本来複数の選択肢を検討してから行われるはずの判断が、検索結果の冒頭にある要約によって短絡化される。そこに登場するか否かが、企業の選ばれる確率を大きく左右しうる構造が静かに形成されています。
このような不確定要素の多い環境下で求められるのは、最適化された解を急ぐことではなく、変化そのものに対する感度を高く持ち続ける姿勢です。情報がどう扱われるか、どう受け取られるか、そしてその過程においてどんな誤解や逸脱が生まれ得るのか。そうした“見えない構造”に目を向けることが、次の行動のヒントとなります。
検索体験の再構築は、企業の情報戦略やコミュニケーションの根底に揺さぶりをかけています。その変化を単なる脅威と見るのではなく、情報との向き合い方を見直す機会ととらえることで、次のステップに進むための準備が静かに始まっていくのかもしれません。