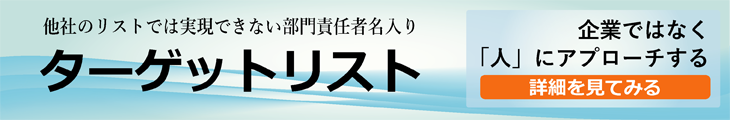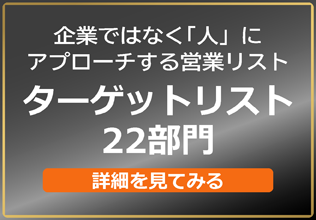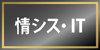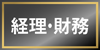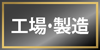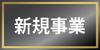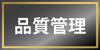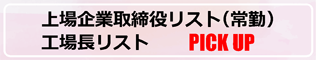2025-04-23
ゼロクリック検索とAI回答にどう対応する? ― クリックされずに価値を届ける方法
BtoB 営業・マーケティング コラム
検索してもクリックされない――そんなユーザー行動が当たり前になりつつあります。検索エンジンは日々進化し、かつてはクリックしなければ得られなかった情報が、今では検索結果の一覧やAIによる要約だけで解決できてしまう場面が増えてきました。Googleの強調スニペット、ナレッジパネル、さらにはChatGPTのようなAIツールの普及が、この傾向に拍車をかけています。
こうした変化は、企業の情報発信にとって大きな転換点です。従来のように「検索結果から自社サイトへ誘導する」ことを主眼とした施策だけでは、ユーザーの目にも留まらないまま埋もれてしまう可能性があります。
では、クリックされない前提でも、どうすれば情報やメッセージを届けられるのか? クリックされなくても「価値が伝わる」コンテンツとは、どのようなものか? 本記事では、ゼロクリック検索とAI回答が日常になった今、どのようにして企業が「届け方」を再設計していくべきかを考えます。
目次
ゼロクリック検索とAI回答の現状
検索結果をクリックせずに、画面に表示された情報だけで用が済む ―― こうした「ゼロクリック検索」が近年増加しています。背景には、検索エンジンの機能強化と、ユーザーの行動変化があります。Googleは強調スニペットやナレッジパネルといった機能を通じて、ユーザーがページ遷移する前に答えを得られるよう設計を進めてきました。
たとえば、「○○とは」と検索すれば、その定義や概要が検索結果の上部に表示されることがよくあります。この段階で疑問が解消すれば、ユーザーがWebサイトを訪れる必要はなくなります。情報へのアクセスが効率化される一方で、発信側としては「クリックされる前に情報が消費される」状況に直面することになります。
さらに、ChatGPTなどの生成AIが普及したことで、検索を介さずに情報を取得するユーザーも増えてきました。キーワードを入力しなくても、自然言語で問いかければ回答が得られる環境が一般化しつつあります。特定のテーマや課題について、検索エンジンを使わずにAIとのやり取りだけで完結する場面も珍しくなくなってきました。
こうした変化は、企業の情報発信の前提にも影響を与えつつあります。従来は「自社のWebサイトにどう誘導するか」が主な課題でしたが、現在ではそれに加えて、「検索結果の一覧やAIの回答にどのように表示されるか」といった視点も無視できなくなりつつあります。クリックを前提としない形であっても、情報が目に触れ、認知され、印象に残ることの重要性が増してきています。
このような環境においては、「表示された一瞬」の中で何をどう伝えるかという工夫が、これまで以上に意味を持ってきているのです。
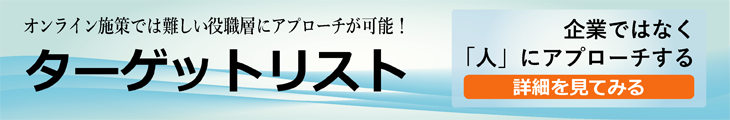
なぜ「クリックされなくても価値を届ける」必要があるのか
クリックされて初めて情報が届く、という前提が成り立ちにくくなっています。ユーザーは検索結果ページやAIの回答だけで疑問を解消することが増え、その場で次の行動へ移ってしまいます。つまり、ユーザーとの接点がWebサイト上にあるとは限らず、「クリックされる前の段階」も立派な情報接触の機会として認識する必要があるのです。
では、クリックされなかった情報は、意味がなかったのでしょうか。必ずしもそうとは言えません。たとえば、検索結果に表示されたスニペットの数行だけで、その企業の専門性や方向性が伝われば、ユーザーの記憶には残ります。次に関連するテーマを調べるとき、あるいは別のチャネルでその企業に再び接触したとき、前に見かけた印象が思い起こされることは十分にあり得ます。
また、企業としての姿勢や考え方が端的に伝わることで、「クリックしたいとは思わなかったが、しっかりしている会社だと感じた」という無意識の信頼形成が行われることもあります。検索経由の行動は必ずしも直線的ではなく、情報がどの段階で印象に残ったかは定量的に捉えづらいものです。けれども、それが後の問い合わせや商談につながることもある以上、無視することはできません。
クリック以外の接点にも意味を見出すことは、コンテンツの役割を再定義することでもあります。従来のように、「クリック率」や「直帰率」だけを評価軸にしていては、目に見えない効果を見落としてしまいます。どれだけ早い段階で、どれだけ適切な形で、どれだけ簡潔に、ユーザーの頭に残るか。そうした視点を持つことで、クリックされなかった情報も「意味のある接触」に変えていくことが可能になります。
表示されること自体に価値を持たせる工夫
クリックされる前の段階で価値を届けるには、「目に触れた瞬間に何が伝わるか」を意識した工夫が欠かせません。検索結果やAI回答に自社の情報が表示されたとき、数秒間でどれだけユーザーの記憶に残せるかが勝負です。そのためには、コンテンツの「見せ方」を戦略的に設計する必要があります。
まず基本となるのは、構造化データの活用です。検索エンジンがページ内容を正しく理解し、適切な形で表示してくれるようマークアップを整備することは、スニペットへの掲載やFAQリストの展開など、ゼロクリック領域への対応に直結します。技術的な対応が求められる部分ではありますが、検索結果に自社の一部がどのように切り出されるかをコントロールするうえで、有効な手段となります。
一方で、構造だけでなく「中身」も見直す必要があります。特に重要なのが、タイトルや冒頭文の設計です。クリックされるかどうか以前に、表示された数行で何を伝えるか。内容を詰め込みすぎず、それでいて企業の立場や専門性が感じられる言葉選びが求められます。言い換えれば、「これだけでも価値がある」と思わせるような冒頭設計が重要になります。
情報の伝達効率を高めるうえでは、FAQ形式や箇条書きといった視認性の高い形式も効果的です。ユーザーが目で追いやすく、頭に入りやすい構成を心がけることで、スクロールせずとも伝わるコンテンツになります。これはAIによる要約対象としても有利に働く可能性があります。
また、「引用されやすい」コンテンツであることも大切です。AIや検索エンジンが回答を生成する際、再利用しやすい文章構造や文体が影響するケースがあるため、簡潔かつ論理の通った説明や、一貫した語調が望まれます。派手なコピーよりも、整理された主張や定義文のほうが引用に耐えることもあります。
さらに、コンテンツの中に自社の視点や考え方を自然に織り込むことも、差別化につながります。単なる情報の羅列ではなく、「この会社らしい」「この立場だから言えること」と感じさせる一文を添えることで、短い接触時間でも印象を残しやすくなります。AIの回答に要約される場合でも、そうした視点は意外と抜け落ちずに残ることがあります。
つまり、クリックされることをゴールに据えるのではなく、「表示された時点で何が届くか」を起点に考える。そうすることで、コンテンツの設計や運用にも新たな軸が生まれます。そしてそれは、検索エンジンだけでなく、SNSのプレビュー、チャットボットでの引用、AIによる再構成など、さまざまな接点にも通用する考え方となります。
クリック以外の評価軸を持つ
クリックされないことを前提に情報発信を考える際、合わせて見直したいのが「何をもって効果とするか」という評価の軸です。従来は、検索からの流入数やクリック率、直帰率といった数値がコンテンツの成果を測る主な指標でした。しかし、ゼロクリック検索やAIの回答が接点となる現在、その指標だけでは実態を正確に把握できない場面が増えています。
たとえば、検索結果に表示された情報だけで企業の存在を認識され、後日SNSやイベントを通じて接点が生まれるケース。あるいは、Webサイトには来訪していなくても、AIツール上での対話に自社コンテンツの一節が引用され、そこから社名やサービスを知るケース。こうした間接的な接触は、数字として現れにくいものの、確実に影響を与えています。
このような接触を捉えるには、評価軸の多層化が不可欠です。たとえば、ブランド想起率、社名の検索ボリュームの変化、SNSでの言及内容、営業現場での企業認知の体感など、定量・定性を問わず複数の視点を組み合わせることが重要です。また、クリックされない情報にも「機能していた証拠」はあるはずで、それを拾い上げる仕組みづくりが必要になります。
あわせて考えたいのが、SEO以外のチャネルとの連携です。SNSやメールマガジン、プレスリリースなど、情報が巡り巡って届くルートは多岐にわたります。検索で一度目にした企業が、別の媒体で再登場することによって記憶に残るという連鎖も珍しくありません。つまり、クリックされなかったコンテンツにも「後から効いてくる役割」があるという視点が欠かせません。
社内においては、こうした見えづらい効果をどう共有し、どう評価に反映させるかも課題となります。数字に表れづらい活動は軽視されがちですが、中長期的な視点で見れば十分な価値があります。可視化しづらい成果をどう言語化し、チーム内や他部署に伝えていくか ―― そこに情報発信の本質的な意義を再確認する機会があるとも言えます。
自社にとっての「届け方」の再設計
ゼロクリック検索やAIによる情報提供が浸透する中で、企業の情報発信は「読んでもらう」から「見られた瞬間に伝える」方向へと重心を移しつつあります。これに伴い、自社の「届け方」自体を見直すことが求められています。ただし、それは一気に大きく変えるというよりも、視点を少しずらし、調整していくような作業に近いかもしれません。
まず取り組むべきは、検索に対する考え方のアップデートです。従来のSEOでは、順位やクリック率を中心に考えるのが主流でした。しかし今後は、「どう表示されるか」「どこでどう切り取られるか」といった視点を設計段階から組み込む必要があります。これは、検索結果だけでなく、SNSやAIツールでの再利用といった二次的な接触経路にも関わってきます。
次に、コンテンツの配置や設計を見直すことも有効です。同じ内容でも、見られる状況によって適した形式は異なります。ブログ記事、ホワイトペーパー、スライド資料、動画、FAQといった異なる形で表現し、それぞれの「見られ方」に合わせて調整することで、届け方に厚みが出てきます。ポイントは「使い回す」ことではなく、「最適化して届け直す」ことにあります。
さらに重要なのは、短い接触でも自社らしさや立場を伝えられるかという視点です。検索結果に抜き出された一文、AIに要約されたひと段落の中に、他社にはない観点や、専門的な視点が盛り込まれていれば、それだけでも印象は大きく変わります。特別な表現や派手な言葉ではなく、整った構成と明確な意図が、最終的には信頼につながっていきます。
情報を「届ける」という行為は、もはやWebサイトやコンテンツを作るだけでは完結しません。検索エンジン、SNS、生成AI、あらゆる場面で情報が切り取られ、再構成される時代においては、どう見られ、どう記憶されるかまでを含めて発信を設計することが求められています。それが今、自社にとっての「届け方」を再構築するということなのです。
まとめ
ゼロクリック検索やAIによる回答が日常の一部になりつつある今、私たちは「クリックされること」を前提としない情報発信の在り方と向き合う必要があります。クリックの有無にかかわらず、目に触れたその瞬間に何を伝えるか。そこに価値を見出す視点が、今後の情報設計に不可欠となります。
検索結果やAIによる要約においても、企業の専門性や姿勢がわずかな文章から伝わることがあります。その一文が信頼や興味を生み、別の場面での再接触へとつながっていく。そうした情報の流れは、もはやひとつのチャネルの中では完結しません。
だからこそ、私たちは発信の形だけでなく、その意味や役割も見直していく必要があります。表示された一瞬にも意図と工夫を込めることで、クリックされなくても「伝わる」コンテンツは実現できます。変化の中で問われているのは、届けたい相手に、どう届くか。その本質的な問いに向き合い続ける姿勢こそが、今求められているのかもしれません。