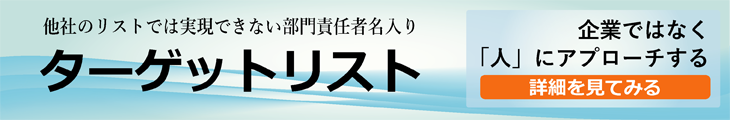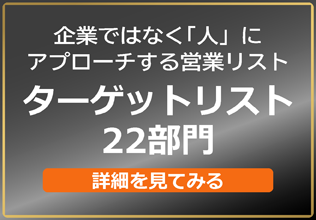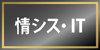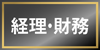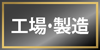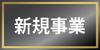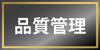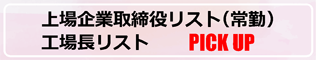2025-04-18
数字より“感情”を聞く ─ 受注確度を高める『エンプシー・セールス質問術』10選
BtoB 営業・マーケティング コラム
営業の現場では、進捗や確度を「数字」で語ることが当たり前になっています。商談件数、提案数、フェーズの割合――これらは組織運営には欠かせない指標です。しかし、こうした定量情報だけでは、顧客の本当の気持ちや決断の動機までは見えてきません。「検討中」「社内で調整中」といった言葉の裏にある“感情”を拾えなければ、提案のタイミングを誤り、せっかくのチャンスを逃すことになりかねません。
本記事では、相手の内面に自然と踏み込むことを目指す『エンプシー・セールス質問術』を10の切り口で紹介します。数字ではなく、相手の気持ちに焦点を当てることで、受注確度の高い対話を生み出すことができます。売り込むのではなく、相手の“考えるきっかけ”をつくる。そのための質問の力に、改めて目を向けてみましょう。
なぜ“感情”に注目すべきなのか
営業活動では、どうしても「どのくらい確度が高いのか」「何パーセントで受注できるのか」といった数字や進捗管理が重視されがちです。しかし、実際の現場で商談が進まないとき、その原因はしばしば数値化できない“感情”の部分にあります。
たとえば「検討中」という一言の背景には、「本当は導入したいけれど社内の反発が怖い」「まだどこか納得しきれていない」「他社と比較して決め手に欠ける」といった、さまざまな感情が複雑に絡み合っています。数字だけを追いかけていると、こうした本音を見落とし、形だけのヒアリングに終始してしまうことも珍しくありません。
このような中で、欧米の営業現場などで注目されてきたのが「エンプシー・セールス」という考え方です。エンプシー(Empathy)は「共感」という意味で、単なる情報収集や問題解決のための質問ではなく、相手の気持ちや葛藤に寄り添いながら対話を深めていくアプローチを指します。自分の提案を通したいという一方的なスタンスではなく、「なぜ今、その答えなのか」「どんな思いでその言葉を選んだのか」といった、相手の内面に目を向けることで、より自然な信頼関係が生まれます。
ビジネスの場であっても、人が意思決定する根底には感情があります。理屈では納得していても、どこかで腑に落ちない感覚が残っていれば、決断は先送りになりがちです。だからこそ、相手が何に不安を感じ、何に期待しているのか、感情の動きを丁寧に拾い上げることが、結果として受注の確度を高める近道となります。
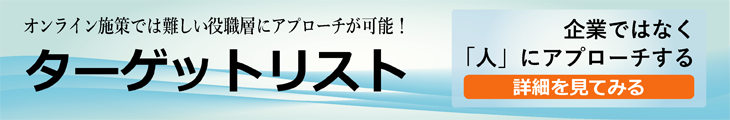
感情を引き出す質問の前提
相手の感情を引き出す質問を投げかけるには、まずこちら側の姿勢が問われます。ただ聞きたいことを並べるだけでは、相手は内面を見せてはくれません。特に営業の場では、「答えたところで何か売り込まれるのでは」という警戒心を持たれていることも少なくありません。
だからこそ大切なのは、「聞く理由がある質問」をすることです。形式的なヒアリングや、マニュアル通りのテンプレート質問では、感情にまでは届きません。相手が語ってくれるのは、「この人は本気で私の立場を理解しようとしている」と感じたときです。
また、質問の中身以上に重要なのが“聞く姿勢”です。相手の話を途中で遮らず、評価も挟まず、ただ丁寧に受け止める。その積み重ねが「この人になら話してもいいかもしれない」という信頼感を生み出します。質問は情報を得るためだけの手段ではなく、関係性を築くための入口なのです。
さらに、良い質問をするためには、事前の準備も欠かせません。相手の業界や立場、これまでのやり取りを踏まえたうえで、「いまどんな状況にいるのか」「どんな葛藤を抱えていそうか」を想像すること。それができて初めて、的確で共感のある問いかけが可能になります。
感情にアクセスするには、ただ質問を増やせばよいわけではありません。問う前に、どれだけ「聞く準備」が整っているか。その前提がすべてを左右すると言っても過言ではないでしょう。
エンプシー・セールス質問術10選
ここからは、相手の感情に寄り添いながら、自然に本音を引き出すことを目的とした質問を10個ご紹介します。いずれも、受注に直結する“情報”ではなく、“気持ち”を聞くことに軸足を置いた質問です。順番に意味はなく、状況や相手に応じて柔軟に使い分けることが重要です。
1)いま、一番気になっていることは何ですか?
最初に確認すべきは、相手の頭の中でいま何が引っかかっているかです。機能や価格ではなく、「気になっている」という言葉を使うことで、感情の入口を開きやすくなります。
2)もし導入するとしたら、どんな状態が理想ですか?
検討段階でも、「導入後」を想像してもらうことで、無意識に前向きなビジョンが言語化されます。相手自身が望むゴールを引き出せれば、その実現に向けた提案の軸が明確になります。
3)導入が難しいとしたら、どんな理由が考えられますか?
あえて否定的な仮定を投げかけることで、相手が抱える不安や懸念を引き出します。こちらが指摘するのではなく、相手に語ってもらうことで、感情の流れを自然に表に出すことができます。
4)これまでのご経験の中で、印象的だった導入事例はありますか?
過去の記憶は、感情と密接に結びついています。成功体験でも失敗体験でも、そこには相手なりの価値観がにじみ出ます。自分の言葉で語られる経験には、今後の判断軸が隠れています。
5)社内で共感が得られそうな点はどこですか?
意思決定の場面では「共感」が動きを後押しする鍵になります。この質問によって、相手自身が“味方になってくれそうな存在”を意識することにもつながります。
6)逆に、反対されそうなポイントはありますか?
抵抗勢力をあえて質問で可視化することで、早い段階から課題の芽を共有できます。表面的な理由ではなく、“なぜその人がそれを嫌がるか”という背景感情まで届くと、対策の立て方が変わります。
7)このタイミングで話を聞いていただいた理由を教えていただけますか?
タイミングには必ず背景があります。忙しい中で話を聞いてくれている時点で、何かしらの期待や問題意識があるはずです。それを相手の口から語ってもらうことで、対話の接点が明確になります。
8)もし導入を見送った場合、どういったリスクがあると思われますか?
「リスク」の話題は、数値よりも感情に根差すことが多い領域です。「このままではまずい」という焦りや不安を言葉にしてもらうことで、優先度や導入動機がより具体化されます。
9)導入が決まるとしたら、誰が最終的な後押しをしてくれそうですか?
キーマンの確認はよくある質問ですが、この問いは“その人がなぜ後押ししてくれるのか”という感情的な要因も含めて考えてもらうことを意図しています。信頼関係や立場の力学が垣間見えます。
10)最後に、私たちに今期待していることは何ですか?
相手の「期待」を聞くことで、関係性をどう築いていくべきかのヒントが得られます。提案の方向性だけでなく、態度・対応へのニーズも見えてきます。感情的期待を認識し、応えていく姿勢は、信頼形成に直結します。
これらの質問は、どれも「売るため」ではなく、「理解するため」に使うものです。回答をそのまま提案に結びつける必要はありません。むしろ、相手自身が考えていなかった気持ちに気づくことこそが、対話の価値になります。
質問を活かす“聞き方”の技術
良い質問をしても、それをどう“聞くか”で結果は大きく変わります。問いかけはあくまできっかけに過ぎず、相手の感情を引き出せるかどうかは、そのあとの受け止め方にかかっています。
まず意識したいのは、相手の話を途中で遮らず、言い切るまで黙って聞くことです。営業の場ではつい先回りして補足したくなったり、沈黙を埋めようと焦ったりしがちですが、“間”を受け入れることは相手にとっての安心材料になります。沈黙のあとに出てくる言葉ほど、本音が含まれていることも多いものです。
また、相手が語った内容にすぐ反論や解釈を加えるのではなく、「そう感じられているんですね」「なるほど、そういう見方もあるんですね」といった共感のひと言を挟むことが大切です。内容をすべて肯定する必要はありませんが、まず感情を認めることで、対話の扉は少しずつ開いていきます。
加えて、相手が言葉に詰まったときに無理に話を引き出そうとせず、その沈黙も「考えてくれている時間」として尊重する姿勢も有効です。「答えても安全だ」と感じてもらえれば、より率直な話が引き出されやすくなります。
問いの質を高めることも重要ですが、それ以上に“聞き手”としてのふるまいが、質問の効果を決定づけます。言葉の奥にある感情の輪郭を、焦らず、丁寧にすくい取ることができるかどうか。それこそが、営業という対話の価値を左右するポイントです。
感情を捉えた後、どう行動に変えるか
相手の感情をうまく引き出せたとしても、それをどう行動に落とし込むかが次の焦点です。共感を得られただけで満足してしまっては、受注にはつながりません。重要なのは、相手の感情から“次の一手”を導き出すことです。
たとえば、「導入したいが社内の理解が不安」という声を聞いたなら、その不安を誰が抱いているのか、何に納得していないのかを深掘りし、その人に届くような補足資料や比較情報を整えることが行動になります。つまり、感情を“ヒント”として扱い、提案の設計や進行に反映させるという視点です。
また、ヒアリングで得た感情の動きは、営業担当者の頭の中だけに留めず、チーム内でも共有しておくことが有効です。数字には表れない情報こそ、他のメンバーの示唆やサポートを引き出す材料になります。共有の際は、「懸念」「期待」「迷い」といった分類で整理すると再現性が高まります。
感情を捉えることは、相手の立場に立った提案を実現するための起点です。その一言にどんな意味があるのかを自分なりに考え、それを手触りのある行動に変換していく。そこに営業としての価値が宿ります。
まとめ
営業という仕事は、「聞くこと」からすべてが始まります。商品知識や業界理解といった武器を持っていても、相手の感情に触れられなければ、それらは的外れな提案で終わってしまうこともあります。数字だけを追う姿勢では見落としてしまう「なぜ迷っているのか」「どこに不安があるのか」といった感情こそが、意思決定の本質に近い部分です。
『エンプシー・セールス質問術』は、相手の内面にそっと触れることを目的とした問いの使い方です。それはテクニックというよりも、関係性をつくるための姿勢に近いものかもしれません。感情を引き出す問いかけには、焦らず、決めつけず、相手の時間に寄り添う姿勢が求められます。
相手の本音に気づくことができれば、次にやるべきことは自然と見えてきます。そのとき初めて、提案の角度も、進め方の順序も変わります。そして、ただの「商談相手」から、「信頼できる相談相手」へと関係が変わっていくのです。
売るための質問ではなく、相手のために聞く質問を。感情を理解する営みが、結果として数字にもつながっていく。この順番を見誤らないことが、これからの営業に求められている姿勢ではないでしょうか。